図書情報室
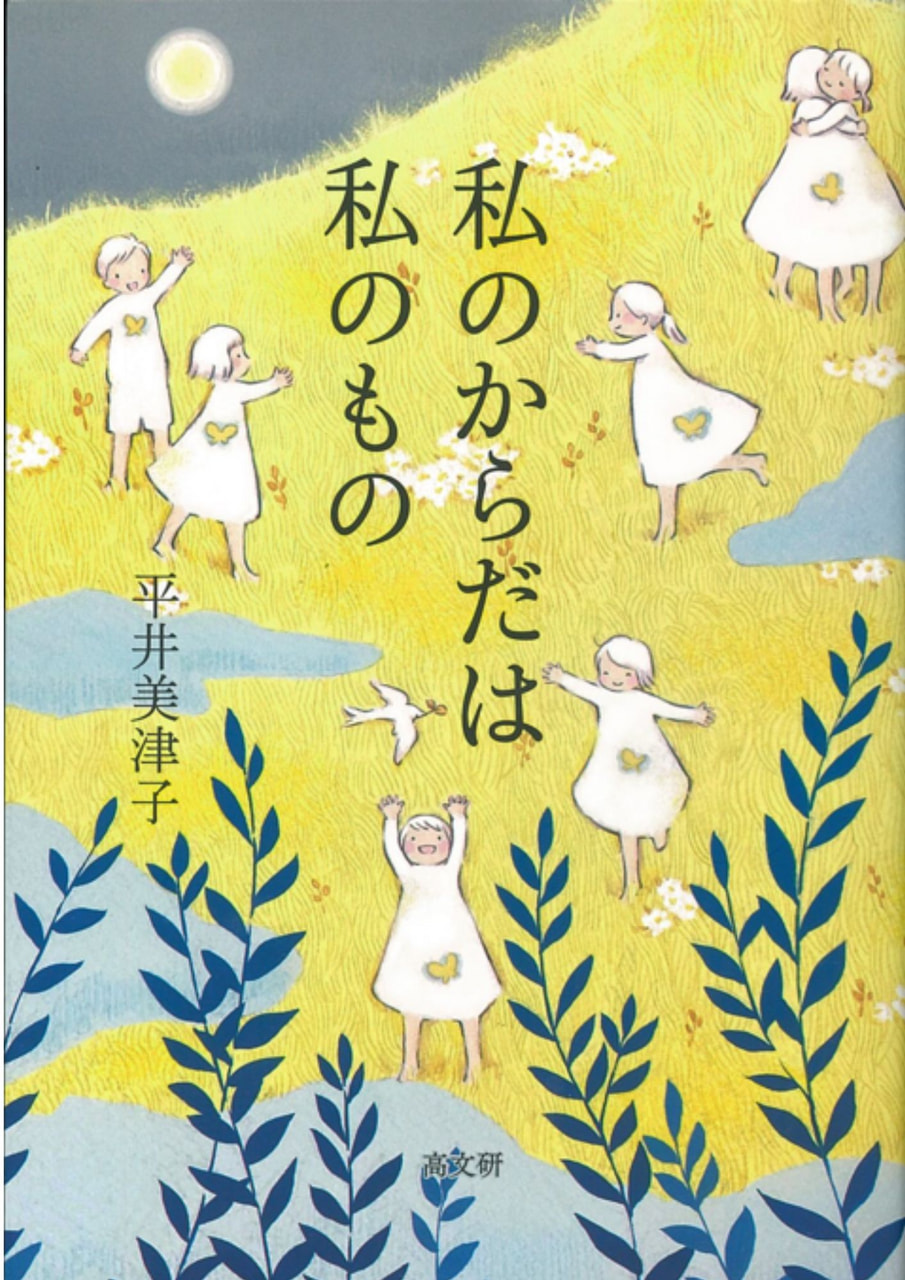
私のからだは私のもの
74/ヒ
高文研
本書は、日本社会に根強く残る「レイプ神話」が、被害者の声をどれほど奪い、追い詰めてきたのかをわかりやすく示している。若い世代ほど神話を受け入れやすいという調査や、性暴力を軽視してきた文化や教育の不足が紹介され、問題が個人ではなく社会全体の構造にあることが浮かび上がる。性売買の歴史や日本軍「慰安婦」制度、教員や政治家による性暴力の事例などを通し、被害者が声を上げるまでの不安や迷いにも丁寧に寄り添う視点が印象的だ。私たちに求められるのは、被害を疑わず、声を受け止め、沈黙を強いる空気を変えていく姿勢である。「私のからだは私のもの」と誰もが言える社会の実現に向け、重要な気づきを与えてくれる一冊だ。
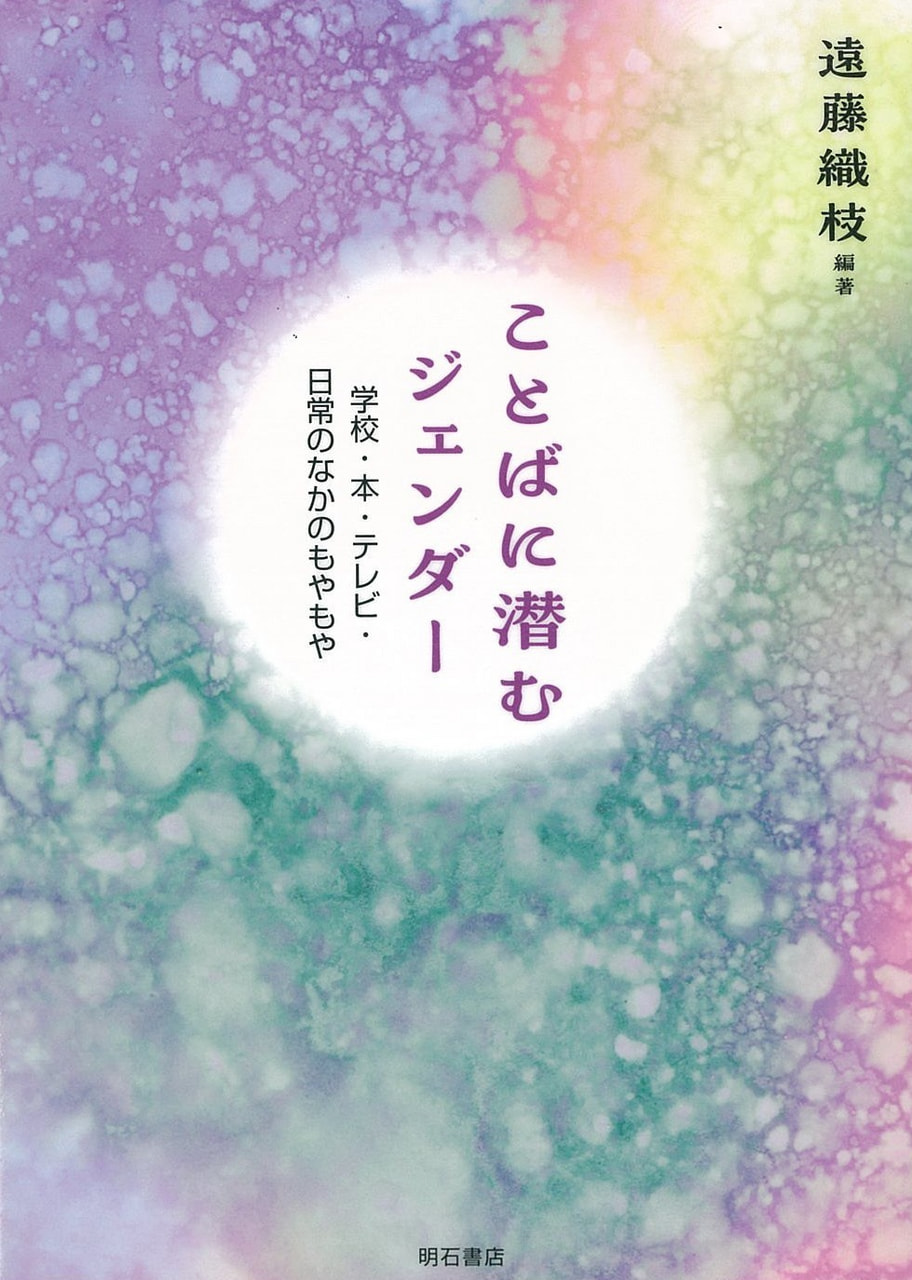
ことばに潜むジェンダー —学校・本・テレビ・日常のなかのもやもや—
124/エ
明石書店
従来の「女らしさ」「男らしさ」の規範意識やいろいろな分野での性差別意識を温存するものの一つに私たちの日常使っている「ことば」があると筆者は言う。小学校の教科書はジェンダーレスになってきているが、その教材を扱う教員や子供たちの家庭、取り巻く社会が変わらなければ、子どもたちには伝わらない。本書では、男女の呼称「さん」「くん」「ちゃん」に潜む問題点や、マンガの男女別のセリフの語尾の書き方やテレビでのジェンダーの表現など具体的な事例を示している。差別的であったり実情に合わなくなったことばを、自分達の表現したい内容を伴ったことばに選びなおし、探し続けていこうと伝えている。
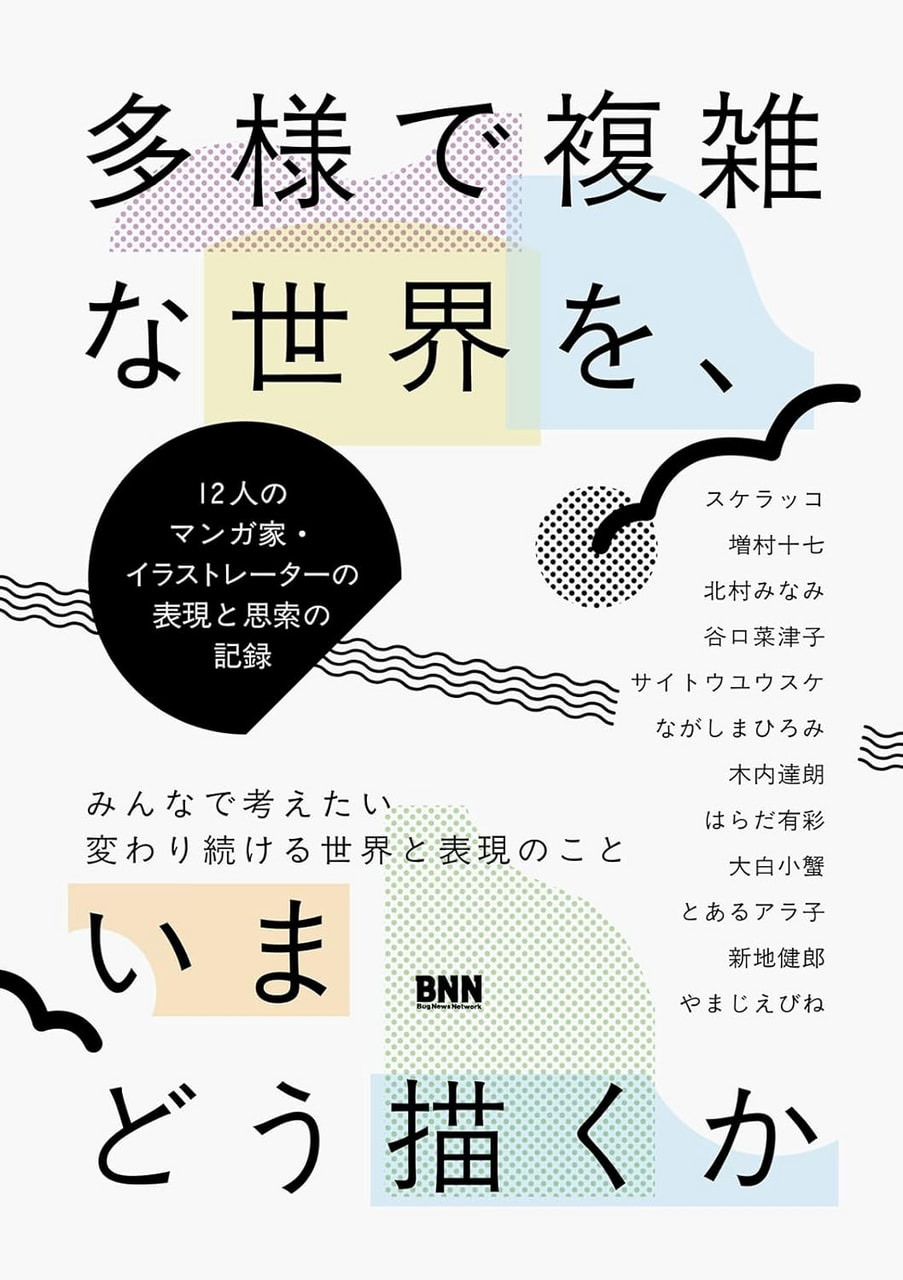
多様で複雑な世界を、いまどう描くか-12人のマンガ家・イラストレーターの表現と思索の記録
15/タ
ビー・エヌ・エヌ
人種やジェンダーなど、多様な価値観が交錯する今、「人が生きる世界をどう描くか」という問いは、表現する人にとっていっそう重く、複雑なテーマとなっている。
本書では、12人の漫画家・イラストレーターが、社会や他者と向き合いながら作品を生み出す過程を語り、そこに込められた粘り強い思索と探求の軌跡をたどる。巻末には識者による多角的な論考も収録され、表現と社会の関係をより深く理解する手がかりとなる。
多様な時代における創作の意味を考えたいすべての人に、静かに響く一冊。
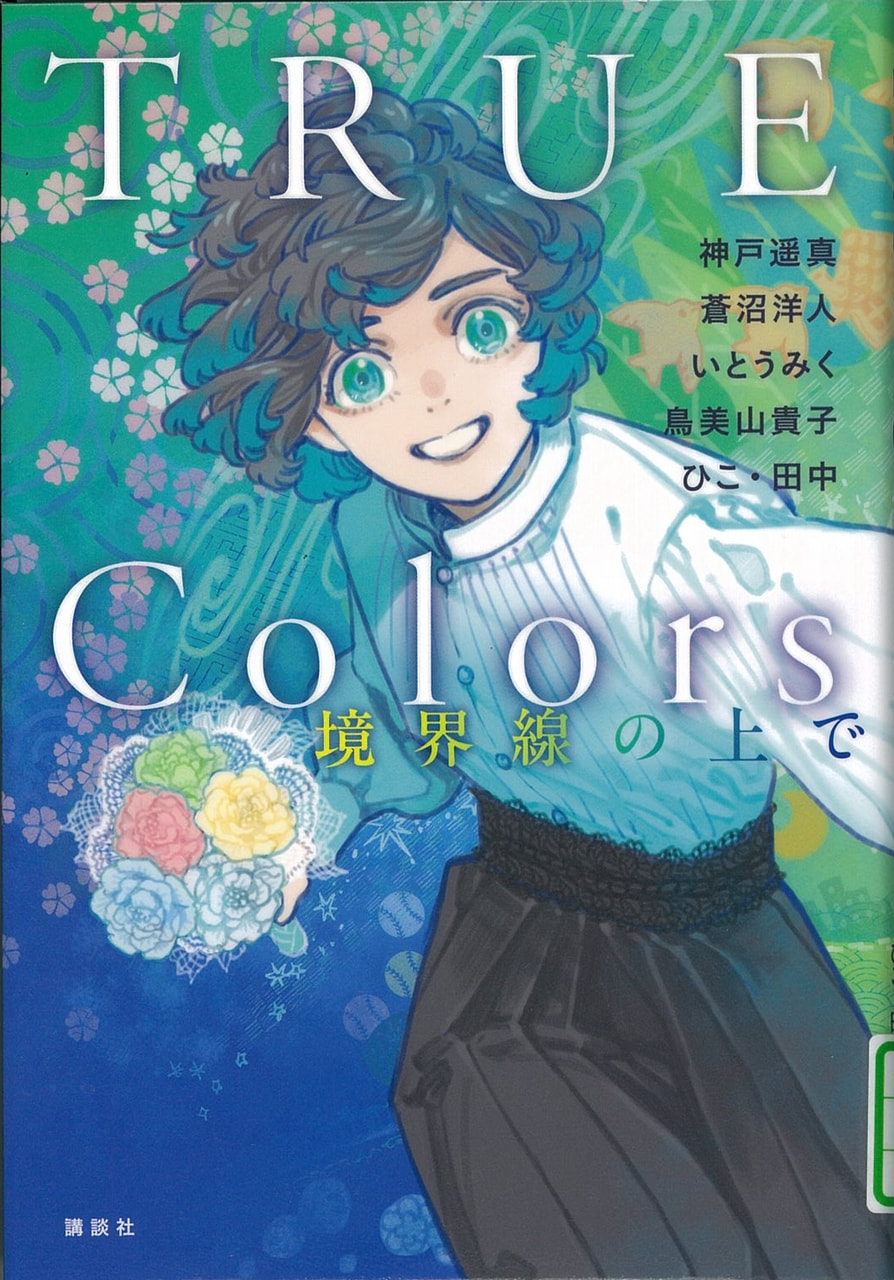
TRUE Colors—境界線の上で—
YA/101/ト
講談社
「女の子は将来ママになるもの」「女の子は甲子園に出られない」「元カレの好きな人は」「誰が家事をするのか」等、子どもたちの日常にある性にまつわるモヤモヤと、それに気づき、逃げずに向き合う姿が描かれるアンソロジーである。創作の世界であっても、現実とは地続きであり、世の中の多様性を知り、そこで起こる感情の動きを体験できる。
図書ラベルのYAはヤングアダルトの略で、大人と子どもの間、主に小学校高学年から中高生向けであるが、どなたでも。子どもの本などと思わず手に取ってみてほしい。
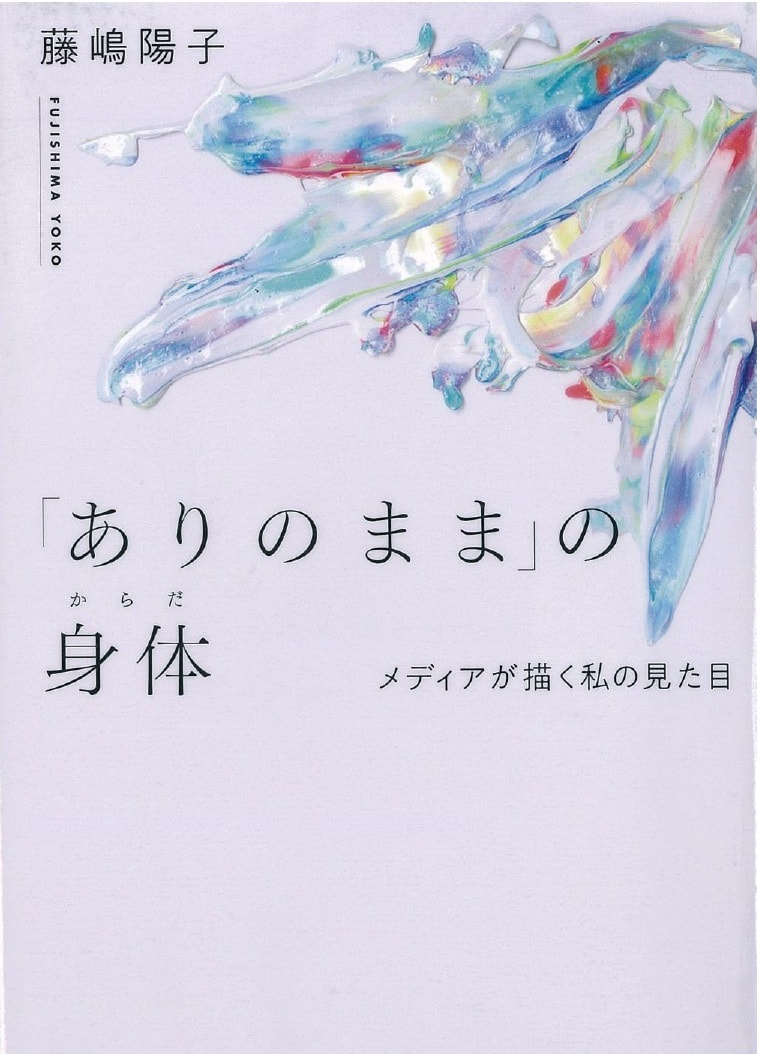
「ありのまま」の身体 —メディアが描く私の見た目—
05/フ
青土社
おしゃれを楽しむことや美容に励むことが推奨される風潮は、メディアの広告戦略やSNS等が影響している。本書は美の規範が進化する現代で“ありのままの身体”を肯定することの難しさを丁寧に分析している。見た目による重圧や偏見は、ボディポジティブ等のムーブメントによる画一的ではない美しさが示された現状でも変わらず、ありのままを愛そうという前向きなメッセージに潜む自己責任論に警鐘をならす考察は、見た目をめぐる葛藤を抱えている人の多様な悩みに寄り添ってくれている。ルッキズムという言葉に包含される問題は根深く、簡単には解決できないが、脱ぎ捨てられない身体を持つ私たちの見た目をめぐる希望と痛みは地続きである、と気づかせてくれる一冊である。
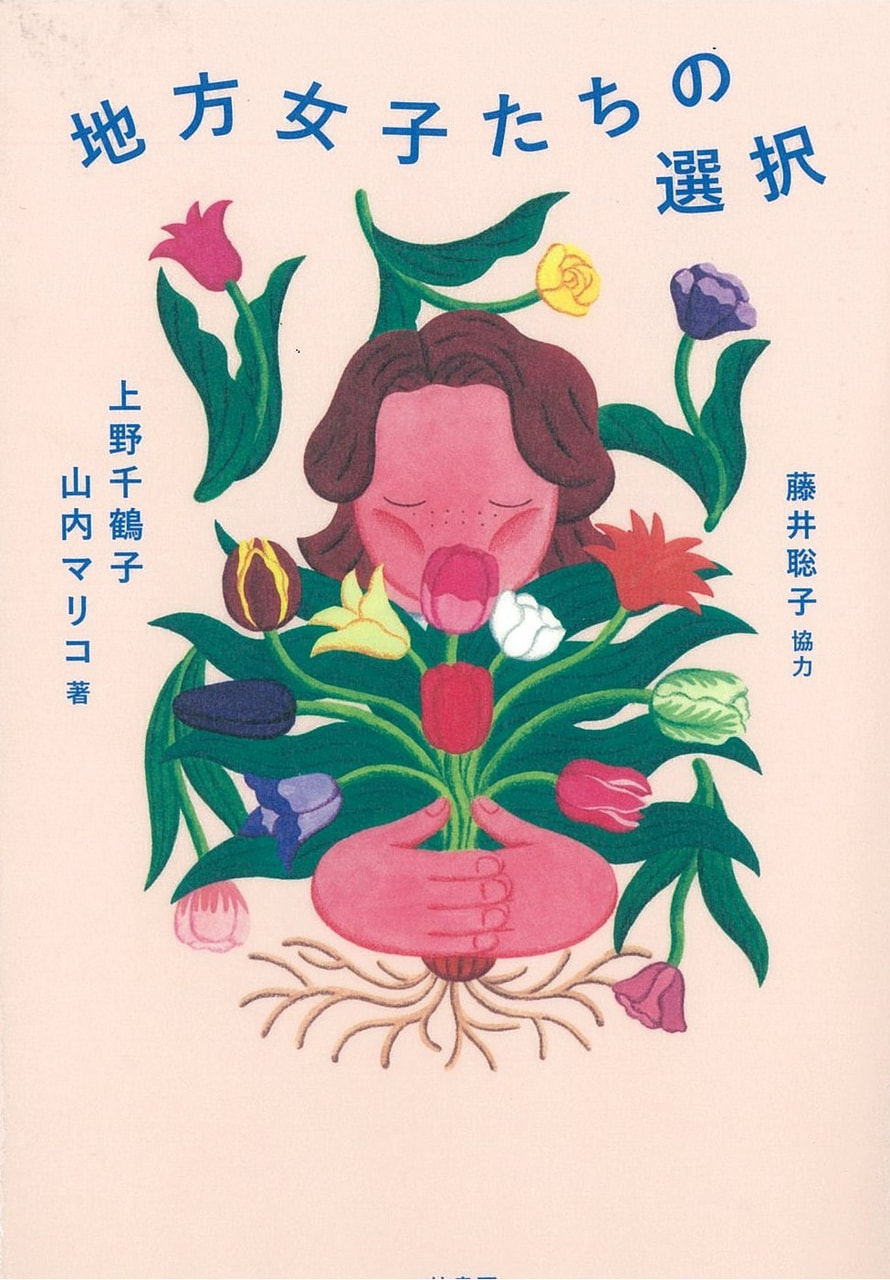
地方女子たちの選択
05/ウ
桂書房
地方から「若年女性」が減っていることが社会問題となってから10年、未だ解決はしないままだ。女性が減ると産まれる子どもの数が減るというが、それは「数」でしか見られていないからではないか。そもそも女性だけの問題なのか。
本書では、地方都市のひとつ富山で世代も環境も違う14人の女性たちが自身のライフストーリーを語る中で、地方都市での“生きづらさ〟や「女だから」と苦しんだり諦めたりしたことが多々みえてくる。著者同士の対談では、ライフストーリーを読み解き、女性を「数」から「生身の人間」へと解像度を上げていく。また、人口減少は、女性の問題ではなく社会の構造的な問題であり、社会に課せられた課題である。女性たちには自信をもっていろんな世界を見て、色んな選択肢の中から自分なりに納得のいく選択をしてほしいと語る。











